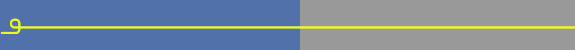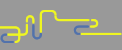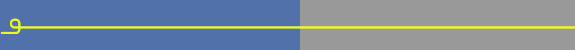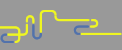2005年04月08日、春うららかな一日が夕暮れに向かう頃、永芳閣に堀浩哉さんは到着した。記憶をたぐり寄せるように一歩一歩を踏みしめて入ってこられた堀さんは、リラックスした出で立ちで久しぶりに出会う永芳閣と自分の記憶を楽しげに待ち受けているかのようだった。

今回の対談は、中村の手がける永芳リライウ゛をプロジェクトのホームページで知った堀さんが、永芳閣への懐かしい記憶とともに永芳リライヴと言う名のアートに興味を抱き、メールで中村に連絡を取った事が始まりだった。こうして永芳閣での中村の対談シリーズが始まった。初回第一弾は堀浩哉さんという事になったのである。
対談の場として用意されたのは永芳閣旅館「天遊」5階の部屋。ロビーで女将、総支配人、取締役と挨拶を交わした堀さんは、中村と女将たちに館内を案内されながら部屋へと向かった。堀さんの記憶の中にある永芳閣は、当然昔の永芳閣であり、今の女将は当時の女将ではない。堀さん、当時は見る事のできなかった裏方や、新しくできた施設など一つ一つの場所を感慨深げに見つめていった。
しかし、新館へ通じる渡り廊下を渡っていくと堀さんは何かを見つけ、吸い込まれるように中へ入っていった。それはカラオケルームだった。新館は12年前に建てられたものであり、堀さんはそれ以前に永芳閣へ来ているという記憶しか語っていなかったはずである。営業前の薄暗なカラオケルームの中に立ち、堀さんは「ここは知っているような気がする、来た事があるような気がする」としきりにつぶやき、記憶をたぐり寄せた。
思いがけず出会ってしまった永芳閣での記憶に落ちつかず、堀さんは対談の部屋に入ると実家へ電話しその事実を確認した。呼び覚まされた記憶は確かなものだった。
実はつい最近、といっても4年前であるが、親戚一同でここへ来ていたのだった。そしてこのカラオケルームで歌っている家族の姿を思い出したのだ。それは父と父の弟である叔父が、肩を組んで実に楽しげに歌を歌う姿だった。叔父は病を患い闘病生活をしていたが、その時は一時的に退院した叔父と親族が集まり、久しぶりにこの永芳閣で食事をしたのだった。その二次会で訪れたカラオケルームで、叔父は昔の歌を一緒に歌おうと父を誘ったのだ。厳格な父が人前で歌を歌うのを見るのは、生まれて初めての事だった。父は叔父の誘いを拒む事もせず、二人は実に楽しげに肩を組んで歌い、孫たちもその姿に喜んだと言う。叔父はその半年後に永い眠りについた。
病身の叔父を気遣いながら、行きなれていた特別な場所として、堀さん家族は永芳閣を選んだのだろう。地元に根付く永芳閣の姿を実感する一面でもあった。
対談は、永芳閣自慢の富樫料理長の腕をふんだんに振るった懐石を食しながら始まった。前日に裏山で採取してきた、青竹の春が瑞々しく先付けを彩っていた。
話に華を添える料理も今日は格段に料理長の遊び心がこもったものであり、対談は互いの経験を語り合いながら進んでいった。

01.アートの二重性
中村:僕の初めて海外は、友達の大学のツアーで行ったニューヨークなんです。当時アメリカ行ったときはとにかく全てがでかくて、「こんなにおおざっぱで良いのか?」と。すごい車が走ってて、「車検て言うのは無いの?」って聞いたら、「無い」って言われて、いや車検が無い国ってものもあるんだと思ってねビックリして。
堀:今、車の話が出たから思い出したけど、90年代の始め頃、僕は中国の敦煌のホテルにいて、ぱっと外見たら見慣れたトラックが走っているんだよ。あの、あのふんどしマーク。佐川急便。中国に佐川急便が進出しているのか!?って、ビックリして慌てて出たの。必死に走って追いかけたの。それで、車が止まったところで、見たら本当にちゃんと佐川急便て書いてあるんだよ。でも、そうじゃないんだよね。要するに、日本で廃車になったようなものが、塗り替えもしないでむこうで使っているんだよ。でもね、敦煌のあんな砂漠の中で佐川急便のふんどしマーク見たときはビックリしたね。
堀:近い経験だと、タイの川縁で普通のボートでエンジンが着いているんだけど、どうみてもでかいの。おかしいな、と思って見てみたら、車のエンジンなの。すごい爆音で、これ車のエンジンついているよ、なんて。それが一台や二台じゃないんですよ。
堀_もう、あらゆる事がハイテクならぬロウテクと言うブリコラージュでまかなっていける、健全と言えば健全なのかもしれないけれど。

中村:堀さんはいろいろと海外に行かれていますけど、海外とかで好きな場所、都市はどこですか?
堀:ローマかな。古代から現代まで、あらゆる時代の都市が廃棄されないまま、層となってすべて重なって、そのまま現代として生きている。あの野方図な強さが好きですね。
中村:僕はメルボルンが割とおもしろかった。オーストラリアの人って非常にコンプレックスを持っていて、僕と屈折度が近い感じがした。
堀:屈折しているからこそ多様性があって、そこがおもしろいのかもしれないね。だけど僕のとても鮮明な記憶では、僕が小学生のころ、当時白人中心の「白豪主義」のオーストラリアが「日本だけは名誉白人にする」という政策を打ち出し、小学校の先生が「大変名誉な事だ」とうれしそうに言った時に、すごい違和感があった。名誉白人に、なんでならなきゃいけないのかって。それがどこかでオーストラリアに対して未だに違和感として残っている所があるんだよね。
中村:でもそういう保守系の人達がいる一方では、それとは違ういわゆる進歩的な考え方は例えば多民族的な文化を大事にしようっていう事がすごく強いですね。でも田舎なんかに行くと、非常に保守的で白人以外を凄く差別する人達も未だにいるんですよ。
堀:やはり何重ものコンプレックスが、複雑な文化を織りなしているんでしょうね。元々はイギリスから島流しにされたような場所だったという事を出発にして、しかし未だに大英帝国の一員であることを堅持しているっていうのは非常に不思議な所がある。そういう歴史の軋みと、アボリジニーに対する迫害とコンプレックスが何重にもなっている訳でしょ。そして、かつて白豪主義をうたっていた人達が、今ではアジアの一員であると言わない限り経済ではやっていけない。いくつもの複雑な精神的な層があって、それらが闘われた結果、文化多元主義的なものが生まれてきたんだよね。だって、それでなきゃ生き残れないからね。だから、とても現代的で面白いとは思うよね。
堀:やっぱりなんでもそうだけど、原理主義っていうのは面白いものは無いんだよね。単一性や原理主義というのはエキゾチズムを誘いはしてもそれ以上ではないからね。他者が入り込めていける面白さっていう事が原理主義の場合無いでしょ。それはアートもそうでね。例えば我々がある作品に「質がいい」と言うときには、極めて原理的なところで判断しているところがある。だからアートは原理主義とは無縁じゃない訳だよね。良い悪いの判定はどこかで原理主義的なところがあるんです。しかし一方で、パラダイムシフト(価値の転換)みたいな事をむしろ積極的に起こそうとすること自体が、アートの価値でもある。それがどちらか一方であったら、アートなんてどっちみち大したものじゃないっていうか、その矛盾する価値の層が複雑に織りなされたものがアートであり、そこにアートの面白さっていうのは出てくるのだと思う。
中村:そうなんですよね。そういう意味だと、オーストラリアのアートシーンというのはまだまだ薄いんですよね。でも、日本の面白さは何かっていうと、質はともかくとしても公募展を含めていい意味での層の厚さがあるから、対するものがちゃんとあるっていうのかな。それは特に公募展や院展等を含めて考えると、僕らからみれば通常のアートとは言いにくいものの価値観のものがあるが故に、逆に言うとコンテポラリーもその他のもっと新しいものも非常にラディカルに出てきていている。日本のアートシーンの面白さは、受験も含めてそうですけれども反面教師の背中があまりにも堅すぎて、僕らの世代が出てきているということの面白さが強さと言うものなのでしょうね。つまり、いわゆる様々な院展から公募展も含むネオだだの人達が出てきて、堀さんたちが出てきて、榎倉さんも含め様々な葛藤の人達が出てきて、一サイクルを終えた。だから両方良い距離を持って見えた時代、対峙しているものだけではなくて自分たちも見えた世代があるところですよ。

02.グローバリズムそのものとどうやって
戦っていこうとするのか。
堀:例えば、現代において全くグローバリズムとは無関係にローカルにだけ生きていけるかと言ったら、現実にはそんな世界はどこにも無い訳で、それでも「俺はローカルなここで生きていければいいや」と言ったって現実にはもう生きていけなくなっている。そういう抵抗はもはやできないのだよね。だからといってそこに身を任せるのではなくて、そこでそのグローバリズムに対してどうやってつきあっていくのか、あるいはそれに対してどう抵抗していくのか、闘っていくのか。今われわれは、それを突き付けられているんでしょうね。「グローバリズムは関係ないんだよ」というのは言えない、当然の事ながらね。
中村:ただ見えているグローバルと見えていないグローバルの問題なんかがあって、目に見えていればいいけれども目に見えていない制度化されてしまい感じにくくなったりしている事や、例えばコンピューターなんかは、今やどの家電にもついてきてしまっている時代で、大雑把にローカルとグローバルを分けられなくなっていますよね。
堀:だからグローバルがあってローカルがあってという、もはや二項対立の話ではないんだよね。グローバルはもはや前提なんだよね。つまりわれわれは受け入れちゃっているんだよ。もっと言えば、グローバルの中にはアメリカイズムみたいなものが当然入っているのだけど、我々はやはりどこかで戦後アメリカの文化に憧れたし、アメリカの基準というもので生きてきたし、どう反発しようとアメリカを前提としてしまった事は事実だ。その中で“違う”と言ったとしても、抵抗するにしても、それを前提とした上での“違う”なんだよね。そうでなかったら単なるローカリズムになっちゃう訳で。それを認めた上で、どう闘うのか。ひょっとしたら最もヤバいのは“グローカリズム”っていうか、グローバルとローカルの融合というヤツだね。旧来の街が櫛欠けになって、空洞化して、郊外に大型スーパーやファミレスやパチンコ屋ばっかりができてきたり、言ってみれば“グローカル”っていうのはああいうものでしょ?地方がみんな東京近郊の小型になっていくように、あるいはみんなニューヨーク近郊の小型になっていきながら、メニューだけはちょっと特産品を入れて、みたいな。
中村:それが“グローカル”の意味での象徴的なシーンでもありますよね。逆に“グローカル”って言ったときの面白さって言うのは、どこに行っても均一なサービスがあり、安心感がある。その安心感を一度体験してしまうと戻れないんだよね。
堀:だから郊外の大型スーパーも現実に使っている人にとっては便利だし、後戻りできないんだよね。後戻りしてローカルに戻れって言うのは全然ナンセンスだし、そういうグローバルを受け入れながら、それでもなお、“融合型のグローカル”を超えた、我々のどこか根源的な根拠を含めたものを発見し、作り上げていかなきゃいけないんじゃないかね。

03.そのとき初めてハイブリッドが起こる
堀:僕が割とよく使う比喩なんだけれども、「日本の絵画はいつ成立したか」って言ったときに、僕はやっぱり“大和絵”というのが一つの成立の契機だったように思うんだよね。これは非常に空想的な言い方なんだけれども、誰が最初に“大和絵”と自らの作品を称したのか、という事を空想する。大和絵以前の日本でももちろん、原始絵画として絵を描いていた人はずっといただろう。けれども基本的に絵画というものは中央(中国)から来たものを、周辺部である日本の絵師たちがお手本として真似して描いていった。最初はそれが絵画だった。中央に対する周辺という意識。でも、最初に自分の絵を“大和絵”と発語した人は、中国から渡来した文化、絵画をただ仰ぎ見る“中央”じゃなくて「ちょっと自分とは違うぜ」と、つまり違和感を感じて、それを“他者”だと思った人だと思うんですよ。でも、“他者”であり“外部”である、そう思った時に、翻ってじゃあ自分は何だろう、“内部”とは何だろうと、改めて思わざるをえない。だって、まだ無い訳ですよ“内部”が。つまり原始的なものはあっても、絵画とよべるものは無かったんだよね。そうすると、これを“中央”じゃなくて“他者”だと思うんだったら、自分たちの“内部”を作らなければならない。“中央”を“外部”だと読み替えて認識したから、初めて“内部”が意識された。これは大変なパラダイムシフトであり、決定的に重要な事件だった。でも“内部”はまだ無い。だからそれを作らなければならない。その時に初めてハイブリッド(異種交配)が起こったんだと思うんだよ。“内部”という根拠が無いのだから、それまでにあった“原始的なもの”と、文化の中心であった“外部”とをハイブリッドさせることでしか、何かを生み出す可能性はない。それが、日本絵画、日本文化の発生だと思うんだよ。日本の文化の優れた特質は、そういうハイブリッドを起こす力にあると、ぼくは思っているんです。中央(中心)と周辺(周縁)という意識、発想のままでは、ハイブリッドは起こらないんです。グローバルとローカルの関係においても、融合型とは違う、そういうハイブリッドをこそ起こさなきゃいけないんじゃないか。
中村:日本の強さは確かにそこですよね。
堀:僕はそれしか無いと思っている。

04.なぜあなたは永芳閣に関わっているのか、
どういった角度で関わろうとしているの?
永芳リライヴについて
堀:中村政人というアーティストがなぜ、老舗旅館の再生計画に関わろうとしているのか、どういった角度で関わろうとしているのか。
中村:広い意味で言うと僕の興味の中では、人の創造力だとか街の創造力だとか誰か何かアイディアを思いついたりだとか、発想する時に今までのものが何らかのきっかけがあって広がる瞬間、その瞬間を見たい、もしくは創りたいという事なんですよね。だから、永芳閣自体が創造力を持とうとするならば、僕が来る前が無い訳じゃないですが、僕が入る事によって更なる主体性をより獲得できるならば、それは見てみたい、創りたいというのがあるんです。僕の作品自体が、どちらかと言うとそういう性格があるんですけれども、自分自身の創造力を高めるという事はある程度分かるのだけれども、ただ対するものがあって初めて自己を確認するように、相手の創造力が高まれば高まる程自分に対しての創造力も高まってくる。創造力って一言で言うと非常に漠然としているのだけれども、それは制度的な問題も含め経済的な問題も含め、様々な事を乗り越えないと本当の創造力は獲得できないと思うんです。その意味で永芳閣が立ち直っていく際に大事なのは創造力だろう、と。永芳閣がいかに主体的になって自分たちの足下から、ある種創造する事の楽しさを自己組織化していくような方向性を獲得していけるのか。そのための基礎トレーニングであったりだとか、変な言い方すると大学だったら基礎教育的な部分であったりだとか、下手するともっと前の予備校で圧倒的に強制的に何かをこなす事で見えてくるものだったりだとか、も含めてこの永芳閣という中にトライしてみたいんですよね。やっている事はと言えばカウンセリング的なものもあるし、ちょっとしたトレーニングを仕掛けてその反応を見たりだとか、ファシリテーター的仕事です。
堀:普通、普通というのがどういう事か知らないで言っているんだけれども、こういう所を再生するとしたら、例えば建物をリニューアルして経営コンサルタントを入れて、コストをカットして直す所は直してとか、つまり経営的な事と建物的な事、それとソフト的な接客とかもあるだろうけど、そういうアプローチとはどう違うアプローチになるの。
中村:つまり経営コンサルタントという意味では、民事再生に通すための弁護士チームというのがあって、民事再生が通った後に僕はよばれている訳ですよね。その呼び方が女将と平田を含め社長が優れている点だと思うんです。これは通常の建築家だとかデザイナーで話をしていっても進まないであろうと。そこで僕を抜擢したセンスをぼくは買いたいと思うんだけれども。(笑)
平田:僕は中村とは同級生で知っていたというのもあるんですけれども、民事再生の裁判で認められ、再生していけるとなった時に、通常のステレオタイプのものをやる事でそこそこのものになるのはだいたい読めたんですよね。これは僕の考えですけれども、アートの力って言うのはファンタジーだけではないって思っているんです。もちろんファンタジーや想像力というものも中村にはあるんですけれども、そこだけに興味がある作家では無いと思っているんですよ。これはアートをやっている自分自身の勘なのですが、ひょっとしたらそれがさっきおっしゃっていたパラダイムシフトを起こしうる触媒になる力を持っているのかもしれないと思うのです。そして、この永芳閣にとって僕は完全に異分子だったわけですけれども、この中にいて見た時に、本当のアウトポジションとしてどういう存在が必要なのか。ステレオタイプなコンサルタントじゃないなと思ったんですよ。
堀:まあ、外部って言うのは常に必要なんですよ。そして今や経営コンサルタントは外部じゃないんですよね。システムの内部なんですよ。そういう意味では、“なぜアートなのか”という問いに対して、“外部として”というのは理解できる訳ですよね。具体的には何をやるのかと言うのが、まだちょっと分からないんだけれども。あなたのほら、湯島の家のプロジェクト。あれは自宅であり仕事場であり、ある種の交流の場であり、同時にそれがアートでもあるという、ある総合的なものを一つの器の中に込めようとして何かをやっているのかな、という気はしているんだけれども、この永芳閣プロジェクトもその辺の事と絡めて何かあるの?
中村:建築的なものに興味は今でも非常にあるけれども、まだまだ納得していないんですよ。街を構成している具体的な姿形を作っている“もの”の生成に対しては、一体誰がどういう理由付けでこの建物を造っているのかというのは、非常に不思議で興味は尽きないんです。そういう発想の中で自分の家を作り出して、“家”というよりも、ある種のコミュニティーを作っているような感覚なんですよ。するとコミュニティーというもののバランスは変化する訳ですよね。自分がいればそこで自分だけれども、自分がいなくなってもそこで自分がいないなりのコミュニティーが生まれてくるのであって、広い意味で言って、コミュニティーを生成するプロセスを促している。永芳閣を形成している部分を刺激していく事により、街と言うコミュニティー全体の変化を促している、またその逆も行っているんです。
つまり僕の精神性とアクションというのは本質的な部分を突いている訳だから、ある意味で永芳閣とはコミュニティー生成において、共犯関係になりうると。
堀:そういう意味では、今までそういう例っていうのは無いんじゃないかね。経営コンサルティング的なものは今やグローバルの時代では内部なんだから、その内部で何をやったって、たかが知れている訳ですよ。成功するかもしれないけど、ハイブリッドは起こらないのだから、これは予定調和の成功ですよ。そうじゃないものが、一方ではアートの顔を持ち一方では現実のコミュニティーの関係性の組み替えとして実現されるとすれば、この資本主義の中ではきわめて特異な例になるのかもしれない。それはやっぱり見てみたいなと思うんだよね。

05.普遍性とは、
「隣の人の中にも自分の幸せがあるかもしれない」と考えたいという、
現在進行形のものの事を言う (堀)
堀:グローバリズムに対抗するマルチカルチュアリズム(文化多元主義)というのは、帝国主義的な世界の一元化や原理主義への抵抗としては意味を持ったかもしれないけれど、一方では単なる言い訳になっているのかもしれない、とも思う。個別性を尊重し世界は多様だということを認めて、そこから出発することはとても重要だけれど、しかしそこに開き直っているだけでは、何の価値も生まれない。普遍を目指さないで、個別性の垂れ流しでしかないものはアートでもなんでもないのと同じように、普遍性というものが全く目指されず、すべての文明、文化が等価ですべからく尊重されるべきというだけでは、文明間の軋轢に対しては傍観者であるほかはないし、柔らかなグローバリズムには手をこまねいているしかない。それは、諦めについての言い訳にしかならないのではないか。またそこでは、原理主義とアプローチは全く逆なんだけれど、どちらの場合も同じように、生産的なハイブリッドは絶対に生じないですしね。
中村:堀さんがおっしゃっている普遍というのはどういうことなんですか?
堀:これは本当は矛盾そのものなんですよね。たった一つの普遍があるということは、もちろんあり得ない。あり得るとすれば、それこそ世界単一の完全原理主義になっちゃうし、一神教の世界観の内部でのことだよね。それを否定しながら普遍性を言うのは、矛盾そのものなんです。でも普遍性があるという前提から出発するのではなく、“目指す”っていうのかな。自分が求めている価値が隣の人にとっても同じ価値であるかもしれない、という事を“目指す”という事以外には、アプリオリに普遍があるとは絶対思わないんです。そうじゃなくて、自分の価値は隣の人も幸せにするかもしれない、自分が良いと思うものは隣の人も良いと思うかもしれない、という事を想像し “目指す”という事だけだよね。隣の人というのは、言葉が全く通じない絶対的な他者のことでもある。それでもなお、それを目指しつづけるという、現在進行形の想像力の事、かな。もちろんね、それで、絶対にそれは嘘なんだよ。つまり“普遍”というものは最初から嘘を含んでもいるんですよ。と、なにか話はとんでもないところへきちゃったけど、これはローカルをどう考えるか、ということでもあるんですよね。
富樫料理長のもてなしも十分に堪能した頃には、既に夜10時をまわっており、氷見の夜はもうすっかり更けていた。
氷見線の終電車に乗ってご実家へ帰宅される堀氏は、帰りしなに永芳閣魅惑のデッド巨大空間スペースを視察した。永芳リライヴのホームページで既に情報を得ていた堀氏は「何か出来そうな空間だ」と思いをめぐらせているようだった。
価値観。それに対してそれが何かの価値であるためには、普遍を目指さなければならない訳だよね。普遍であり得ない、多様であって絶対に一つになり得ないものは、価値であるという矛盾を最初から欠いているんだよね。氷見をめぐる、堀氏と中村の付き合いはまだまだ続きそうだ。 |